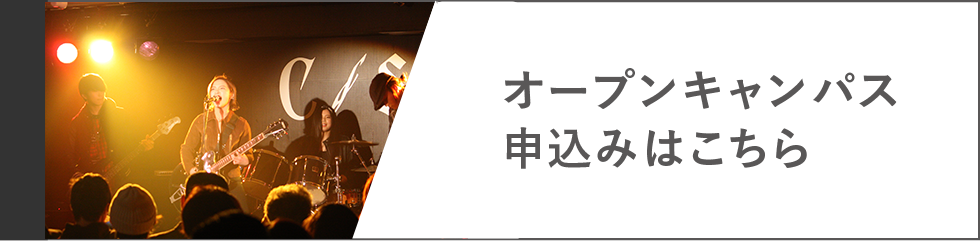「創造して、社会化する。」= これからの時代に求められる力
C(Creative=創造):
表現や制作を通して、自分の個性や特性を深く探り、新たな価値を生み出します。
その過程で「自分をリスペクトする力(自己理解・自己肯定感)」を育てます。
S(Socialize=社会化):
創造した価値を社会とつなげ、他者と関わる中でさらに成長していきます。
その中で「他者をリスペクトする力(共感力・協働性)」を学びます。
こうした力を育てるには、認知能力と非認知能力の両方をバランスよく育むことが不可欠です。
認知能力とは?
国語・数学・英語など、高校卒業に必要な学力=情報処理や知識の活用力です。
進学や就職の際に土台となる、いわば「社会の入り口に立つための力」です。
非認知能力とは?
自己肯定感、創造力、コミュニケーション力、主体性、粘り強さといった、数字では測れない人間としての“内なる力”のことです。
社会の中で「どう生きるか」「誰と、どんな関係を築くか」に直結します。
「創造して、社会化する」ことを通して、生徒は自分の考えや価値観を育て、「自分の軸」を築いていきます。
私たちは、こうした力こそが、これからの時代を生き抜くために大切になると考えています。
目の前の「ひとり」を見つめる学校でありたい
 C&S学院は、少人数制を大切にしています。
C&S学院は、少人数制を大切にしています。
大きな学校では、どうしても一人ひとりの個性や悩みが見えにくくなりがちです。
本当は誰かに気づいてほしい。
そんな想いを抱えたまま、声にならない生徒もいます。
だからこそ私たちは、目の前の「ひとり」と丁寧に向き合います。
小さな変化に気づき、ふとしたつぶやきにも耳を傾ける。
そして、長所を見つけ、伸ばしていく。そんな「ひとり」との関わりを大切にしています。
これまでも、多くの生徒が
「この学校で変われた」「ここに来てよかった」と話してくれました。
その言葉が、私たちにとって何よりの原動力です。
どうか、この学校との出会いが、大切なお子さまの未来をひらく一歩になりますように。
心から、そう願っています。
高等専修学校 C&S学院
学校長 松本 雅昭
【学びの目的・教育理念】「この学び方で、本当に将来につながるの?」
A:本校では、「好きなこと」は単なる娯楽ではなく、自己理解や自立につながる重要な入り口だと考えています。生徒たちは創作や表現を通して、「自分を知る」「選ぶ力」「仲間と関わる力」などを育んでいます。こうした力は、職場でも家庭でも求められる“人間力”であり、社会とつながりながら生きていく土台になると本校は捉えています。
A:そう感じるのはもっともなことです。もちろん、職業に必要な力を育てることも大切です。でも本当に大切なのは、子どもがどんな道を選んでも“自分らしく生きていける力”を育てることだと私たちは考えています。表現や創作を通じて育まれる、自己理解・他者理解・選択力・行動力などは、どんな職業にも通じる普遍的な力であると捉えています。
A:そう感じるのは自然なことです。ただ、社会のあり方は大きく変わってきています。本校では、変化の多い時代を生きるためには、「答えを探す力」よりも「問いを立て、自分で動き出す力」が必要だと考えています。だからこそ、表現や創作を通じた実践型学びを通して、生きる力の土台を育てていきます。今の時代に合った学びを、一緒に考えていけたらと思います。
A:多くの保護者も心配されています。本校では、表現や創作を通じて「自分の考えを形にして伝える力」を育てています。また、プレゼンやプロジェクトの中で、計画を立ててやり遂げる力や、仲間と協力する力も自然と身についていきます。さらに、人を助けたり、困ったときに相談できるような関わり方も大切にしています。こうした力の積み重ねが、卒業後の自立につながると本校は考えています。
【学習内容・スタイル・卒業】「学力は大丈夫?高校としてちゃんと成り立っている?」
A:はい、あります。国語・数学・英語など、高校卒業に必要な74単位を取得できるカリキュラムを組んでいます。担当教員が進度をしっかり把握しながらサポートしますので、ご安心ください。
A:本校では「好きなことの学び」と同時に、「自分らしく生きるための力」を育むことを大切にしています。生徒は自分の好きなことを起点に、創造力や協働性、主体性といった人間力(非認知能力)を育てています。もちろん、社会に生きるための学力基盤(認知能力)も欠かせない力だと考えており、両方のバランスを大切にしています。これからの時代に必要な力を、日々の学びの中で育んでいます。
A:本校には、週5日登校の「全日スタイル」と、週1〜3日登校+オンライン学習を組み合わせた「通信スタイル」があります。生徒の状況に応じて学び方を選べる仕組み(登校スタイルの変更は年度毎)となっており、学びの本質は「どれだけ登校するか」ではなく、「どんな学び方で、自分を成長させるか」であると考えています。
A:通信スタイルでは、登校以外にバーチャル校舎(オンライン空間)を活用し、動画視聴による学習(高校授業)に加えて、担任との面談や課題提出も行います。リアルとオンラインをつなぐハイブリッド型の学び方も、社会で求められる柔軟性につながると考えています。
A:高校卒業に必要な基礎学力(国語・数学・英語など)については、しっかりと時間を確保しています。大学受験に特化した授業は設けていませんが、希望する生徒には、併修しているクラーク記念国際高等学校のWEBコンテンツを活用し、中高の学び直しや受験対策プログラム(※別途費用あり)を空き時間などで取り組むことも可能です。
A:専門授業(音楽・ダンス・声優・イラストなど)では、生徒自身が学びたい内容を選んで進めるフリースタディー(生徒主体型)と、専門講師から基礎技術や知識をしっかり学ぶレクチャー(講師主導型)の2つを自由に組み合わせることができます(通信スタイルはフリースタディーのみ)。
A:C&S学院(専修学校高等課程)での表現や創作の授業に加え、クラーク記念国際高等学校との併修によって、通信高校としての高校卒業資格も取得できる仕組みです。特に、幼少期から学校に通えなかった生徒が無理なく卒業までたどり着いた事例もあり、安心して学び続けられる環境づくりを重視しています。
【進路・将来】「進学や就職に不利にならないか心配です」
A:卒業後は、進学約6割、就職約2割、その他(留学や起業、アルバイト、本校の専攻コースなど)が約2割です。高等学校卒業資格が必要な進学や就職でも、指定校推薦や自己推薦などの制度もあります。また、音楽系の専門学校に進む生徒も少なくありません。
A:本校では、音楽やダンスでプロを目指す生徒に向けて、オーディションの機会など、実力を磨ける環境を整えています。実際に、在学中に音楽会社でインターンを経験し、そのまま就職につながった生徒もいます。また、これまでの20年以上の実績の中で、少人数だからこそ1年半に1人のペースでメジャーデビューを果たした生徒もおり、現場に近い学びを大切にしています。
A:進学実績もあり、クラーク高校の指定校推薦や自己推薦で大学・短大・専門学校に進む生徒も多いです。また、就職についても、新卒枠や学校推薦、さらに在学中の実績(インターン)を活かした就職も実現しています。むしろ、自分の強みを理解し、言葉で伝えられる力を身につけているからこそ、進路選択において柔軟で強いと考えています。
A:本校では、進路に「ひとつの正解」があるとは考えていません。むしろ、進路は「自分で決めるもの」であり、誰かに決められるものではないからこそ、生徒自身の意思で選ぶことを大切にしています。もちろん、卒業後に困らないよう学力の基盤は保証していますが、「人生が全てで決まってしまう」と思い込む必要はありません。
A:本校でいう「第三の選択肢」とは、進学や就職以外の、自分らしい生き方を模索する進路のことです。たとえば、起業、フリーランス活動、ギャップイヤー(自分を見つめ直す時間)、留学、アルバイトを続けながらやりたいことを探す、などが挙げられます。どれも、生徒が自分の軸を持ち、自分で選び取ることを大切にしている進路です。
【生徒の個性・特性への対応】「うちの子に向いている?個性を理解してくれる?」
A:はい、大丈夫です。本校には、小・中学校で不登校を経験した生徒が約7割在籍しています。安心して通える雰囲気づくりを大切にしており、少人数だからこそ一人ひとりのペースに合わせた対応が可能です。
A:もちろんです。発達特性のある生徒も在籍しており、1つのチームとして、スクールソーシャルワーカー(臨床心理士)や教職員、保護者が連携しながら、一人ひとりの状況に応じた丁寧なサポートを行っています。安心してご相談ください。
A:多様な生徒が在籍しております。不登校経験もあれば、進学校や特技推薦を辞退して入学した生徒もいます。共通しているのは「好きなことを通して、自分らしい学びを求めていること」です。見学や体験授業を通じて、学校の雰囲気を実際に確かめ判断していただくことができます。向いているかどうかは、まず一歩踏み出してみてください。
A:本校では、個性を大切にすることと、何でも許す“甘やかし”は違うと考えています。たった一つの校則「人としてのマナーを守ること」を大切にしており、「自由」と「責任」は常にセットであるという姿勢を、生徒たちに丁寧に伝えています。生徒は、好きなことに夢中になりながらも、人との関わり方やマナー、社会の中での立ち位置を自然に学んでいきます。たとえば、発表の場では、相手の受け取り方を考えたり、仲間の意見の違いを経験したりする中で、社会性が育まれています。個性を尊重しながらも、社会の中で自分らしく生きていくための力を、しっかりと育てていく環境を本校は大切にしています。
【学校の雰囲気・人間関係】「人との関わりは?安心して通える?」
A:生徒同士の距離が近く、上下関係のないフラットな雰囲気です。「好きなこと」を通じて自然と仲良くなれる環境があり、発表イベントなどの機会を通して、気づけば友達ができている生徒が多いです。
A:はい、大丈夫です。本校は少人数制で、生徒一人ひとりのペースや特性に合わせた個別対応を大切にしています。大勢の前で話すことや仮に過ごすことが苦手な生徒には、別室で休んだり、授業を受けたりすることも可能です。また「安心して通えること」を一番に考え、無理のなかった学校生活に慣れていけるようサポートしています。人との関わりも、自分のペースで少しずつ広げていける環境です。
A:校則はとてもシンプルで、制服はありません。髪色も自由、ピアスもOK。法律や地域の範囲内であれば、見た目で生徒を縛るルールは設けていません。その代わりに、たった一つ大切にしていることがあります。それは、「人としてのマナーを守ること」です。見た目よりも中身を大事にしながら、「相手を思いやる気持ち」を、日々の学校生活の中で自然に学んでいきます。“自由”の中にも“責任”がある。そうした価値観を、生徒たちは日々の経験を通して身につけています。
A:教科指導のある教員に加え、音楽・映像・ダンス・声優などの分野で活躍してきたプロが講師として関わっています。生徒一人ひとりの個性や状況に寄り添い「長所を伸ばすこと」を真剣に考え、寄り添うスタッフがそろっています。また、本校の理念「創造して、社会化する」を実践し、自ららしく進路を切り拓いてきた卒業生が、今は講師として生徒たちの学びを支えている場面もあります。進路や心のサポート体制も整っており、安心して相談できる環境づくりを大切にしています。
A:はい、あります。C&S学院では、「C&Sコレクション」や「文化祭」など、生徒の表現を発揮できる発表イベントを年に数回開催しています。自分の作品やパフォーマンスを人前で披露する経験が、大きな自信につながっています。また、部活動もアコースティックギター部やダンス部など、生徒のやりたいことを主体的に活動しています。放課後も、生徒同士でゲームをしたり外で体を動かしたりと、それぞれが自分らしく過ごしています。「がんばる時間」も「ゆるやかな時間」も、自分のペースで楽しめるのがC&Sの良さだと考えています。
【学費・通学・生活面】「費用や通学面が心配です」
A:学費の詳細については、オープンキャンパスまたは資料請求にてご案内しております。また、必要に応じて各種奨学金や学費支援制度のご相談も承っております。
A:はい、使えます。C&S学院は「学校法人」専修学校高等課程ですので、通学定期(学割)の対象となります。公式窓口機関で、学割証明書をご利用いただけます。
A:はい、通えます。これまでも熊本県や山口県などから通学していた生徒がいます。そのため、授業は朝10時スタートに設定しています。また、提携している学生寮のご紹介も可能です。詳しくはお気軽にご相談ください。
【保護者との連携】「学校の様子が知りたいです」
A:はい、ご安心ください。本校では保護者の皆さまと連携しながら、生徒の成長を一緒に見守っていくことを大切にしています。年に1回の保護者会(希望制)では、学校での様子や取り組み、進路についての情報を共有しています。また、必要に応じて個別面談やご相談にも随時対応しております。日々の小さな変化にも目を向け、丁寧にサポートさせていただきます。
<私たちの行動指針>
1.生徒の幸せを第一に考える
2.生徒から学び続ける
3.自らを磨き続ける(ブラッシュアップ)
4.変化に合わせて進化し続ける(アップデート)
私たちは、「生徒の幸せ」は大人が決めるものではなく、生徒自身が描き、つかみ取るものだと考えています。
だからこそ、生徒の声に耳を傾け、何が本当の幸せなのかを共に探し、学び合いながら歩んでいく学校でありたいと願っています。
また、社会は日々変化しています。その中で生徒が自分らしく、しなやかに生き抜いていくためには、私たち自身も立ち止まることなく、自らを磨き続け、変化に合わせて進化し続ける姿勢が欠かせません。
生徒と共に成長する存在であること。それが、私たち教職員の在り方です。
C&S学院に入学してくる生徒たちは、
思春期ならではの過剰なエネルギーに戸惑っていたり、
学校や家庭、社会の中での見えないプレッシャーに押しつぶされそうになっていたりします。
「こうあるべき」「○○しなければならない」といった固定観念に縛られ、
人からどう思われるかが気になって自分を出せなくなることもあります。
中には、自分の殻に閉じこもり、教わることを拒み、すべてを自己完結してしまうような状態にある生徒もいます。
そして…
一見元気そうに見える生徒たちの中にも、心の奥にはたくさんの“圧”が溜まっていることがあります。
その圧が限界に達したとき、
他人を攻撃してしまったり、自分を責め続けてしまったり、何もやる気が出なくなってしまうといった形で、心のバランスが大きく崩れてしまうこともあるのです。
だからこそ私たちは、生徒たちが好きな「表現」や「創作」を通じて、心の“圧”を少しずつ抜いていく「解放の時間」を大切にしています。
感情を無理に閉じ込めず、カタチにして外へ出すこと。
それは心のバランス(調和)を取り戻し、やがて思いがけない「変化」として表れてきます。
こうした経験を重ねる中で、
生徒たちは「崩れても戻れる」「揺れても立ち直れる」レジリエンス(回復力)を身につけていきます。
この力は、変化の多い社会をしなやかに生きる“人間力”につながると私たちは考えています。
こうした内なる力(非認知能力)は、これからの時代を生きる力になると信じています。
「表現」や「創作」に取り組むプロセスには、“生きる力”(非認知能力)を自然に育てる力があります。
実は今、世界中でこの非認知能力の重要性が見直されています。
たとえば、ハーバード大学「Project Zero(Howard Gardner)」では、創作活動が深い内省を促し、非認知能力の発達に効果的であると示唆されています。
OECDの「Education 2030プロジェクト」では、芸術活動が共感・責任・関係性といった社会的スキルを育てると明記されています。
「アート思考(Art Thinking)」では、表現の中で問いを立て、自分の価値観を探る力が育まれるとされています。
さらに、グリット研究で知られるAngela Duckworthは、好きなことに情熱を持って取り組むことが、非認知能力の発達と強く関係すると報告しています。
これらの研究をふまえながら、私たちC&S学院でも、表現・創作を通じて非認知能力を育てる教育に力を注いでいます。
自分を知る力(自己理解・自己肯定感)
詞を書く、曲をつくる、絵を描く。自分の内面と向き合い、表現することで、「自分を客観的に見る力=メタ認知」が育ち、自己肯定感の土台がつくられていきます。
人とつながる力(共感力・協働性)
作品をつくる、見せる、語り合う。その過程で、自分と違う価値観に触れ、共感や対話、協力の力が育まれていきます。
主体的に考える力(創造力・探究心)
「何を伝えたいか」「どう表現するか」正解のない問いに向き合い、自分の視点で考え、表現していくことで、“自分の軸”が育っていきます。
やり抜く力(粘り強さ・達成感)
創作には失敗や行き詰まりがつきものです。それでも繰り返し向き合い、乗り越えた先にある「できた!」という達成感が、やり抜く力と自信につながります。
C&S学院では、こうした体験を、日々の授業の中で積み重ねています。「好きなこと」から学びを始め、仲間とつながり、悩み、乗り越える。そのプロセスこそが、「創造して、社会化する」力を育てるのです。
これからの時代をしなやかに、自分らしく生きていくために、生徒一人ひとりの“生きる力”を、表現と創作を通じて育てていきます。
C&S学院では、「表現」や「創作」を通して、生徒たちが自分自身の内側にある“個性”や“特性”と向き合いながら、少しずつ「自分の軸」を育てていけるようサポートしています。
とはいえ、いきなり「自由にやってごらん」と言われても、どう動いていいか分からず、不安になる生徒もたくさんいます。だからこそ私たちは、学びの出発点として“型”を用意しています。
ここで言う“型”とは、決まりきった方法を押しつけるものではありません。
「こうすれば進めやすいよ」という“足場”のようなもの。生徒が安心して最初の一歩を踏み出せるように、基本の手順やテーマをあらかじめ用意しています。
<表現・創作活動の3ステップ>
① やってみる(挑戦の一歩)
まずは、音楽・映像・イラスト・声優・ダンスなど、自分の興味のあることに「触れてみる」ことから始まります。
その“やってみる”という小さな一歩が、生徒にとっては未来を広げる大きなきっかけになるのです。
② みつける(自分らしさの発見)
体験を重ねる中で、自分に合ったもの、夢中になれることが見えてきます。ここで大切にしているのは、他人と比べることではなく、自分の“内側”にある感覚に気づいていくこと。自分なりの「好き」や「得意」を見つけていくプロセスそのものが、自己理解や自己肯定感を育てる土台になります。
③ カタチにする(社会とつながる)
見つけた“自分らしさ”を、作品やパフォーマンスとして表現します。音楽や創作、発表などを通じて「自分はここにいる」と感じることができ、さらにその想いや作品を通じて、他者とのコミュニケーションが生まれ、社会とつながる経験へと広がっていきます。
この3つのステップを繰り返す中で、生徒たちは「自分の軸」を少しずつ確かにしていきます。
そしてその“自分の軸”がやがて、自信となり、生きる力へと変わっていくのです。
生徒たちが「ここなら大丈夫」「自分を受け止めてもらえる」と感じられる環境がなければ、心を開いて自由に表現や創作に挑戦することは難しいと思います。だからこそ、私たちは何よりもまず“安心できる居場所”づくりを大切にしています。困ったときに気軽に相談できる。うまくいかなくても、またやり直せる。そんな環境があるからこそ、生徒は自分らしく挑戦できるようになります。
私たちは、生徒との関係を“先生と生徒”という枠にとどまらず、「人と人」として向き合うことを大切にしています。また、臨床心理士の資格を持つスクールソーシャルワーカーを配置し、医療機関との連携も含めた専門的な支援体制を整えています。
入学して間もない頃、生徒たちは「こんな学校初めて!」「毎日が楽しい!」と目を輝かせています。けれど、日が経つにつれ、慣れや惰性から「なんだか最近、楽しくないかも…」と感じ始める時期がやってきます。これは決して特別なことではありません。誰にでも起こる“心の変化”です。
そんなとき、私たちが生徒に問いかけるのは…
「楽しさって、誰かがくれるもの? それとも、自分で見つけていくもの?」ということです。
ただ待っているだけでは、楽しさはやってきません。
「今、自分はどうしたいんだろう?」と立ち止まり、自分の気持ちを見つめ、自分から一歩を踏み出す。
その姿勢が、これからの社会を生き抜くうえで、何よりも大切な力になると、私たちは信じています。
この考え方は、卒業生たちが教えてくれました。
社会に出て、時には自分の希望とは違う環境や仕事に直面しても、彼らは「どうしたら自分らしく楽しめるか?」を考え、行動し、自分なりのやりがいや喜びを見つけていきました。
だからこそ、私たちは「楽しさは自分で取りにいくものだよ」と伝え続けます。
この学校での毎日の小さな挑戦が、未来のどんな場面でも自分の人生に向き合うための“土台”になっていくと信じているからです。
子どもたちが過ごす学校での時間は、やがて自分の足で生きていく“社会”へとつながる大切な準備期間。だからこそ、私たちの学校は、すべてを守る“無菌室”のような空間ではありません。
社会に出れば、自分とは違う価値観や立場の人と出会い、ときには意見がぶつかることもあります。けれど、そうした“違い”や“衝突”を経験するからこそ、相手を知ろうとしたり、自分の立場を見直したりすることができます。それは、これからの時代を生き抜くための「人との向き合い方」=“免疫力”のようなものです。
ただし、免疫をつけるためとはいえ、いきなり強い刺激にさらされてしまえば、心が傷つき、立ち上がれなくなることもあります。だからこそ、C&S学院では、生徒たちがもし失敗したとしても、安心して戻ってこられる「網」を張っています。
保護者の皆さまと学校とが信頼でつながり、生徒にとっての「安全基地」を一緒につくっていく
そのタッグこそが、C&S学院の教育の土台となっています。
私たちは、教室の中だけで完結する教育ではなく、
“今ここ”の学校生活が、社会で生きる力に直結するような学びを、これからも大切にしていきます。
C&S学院には、たった一つの校則があります。
それは「人としてのマナーを守ること」。
この一言の中には、私たちが大切にしているすべての姿勢が込められています。
たとえば、いじめは絶対に許しません。
また、暴力によって問題を解決しようとする行為も、決して認めません。
それは単にルールだからではなく、人として当たり前のマナーであり、生きていくうえでの土台となる意識だからです。
自由な学びや表現を大切にしているからこそ、私たちはこのたった一つの約束を、すべての生徒と丁寧に向き合いながら伝えています。
自由には責任が伴います。
それは、「他者」という視点を持ち、自分勝手にならずに、他人を尊重するということ。
たとえば、音楽の「バンド」を想像してみてください。
どんなに技術のあるヴォーカルがいても、周りの音を無視して自分だけを主張すれば、音楽は成り立ちません。
でも、それぞれが自分の役割を理解し、互いの音に耳を傾けながら音を重ねることで、初めて“ハーモニー”が生まれ、心を動かす音楽になります。
学校生活も、まさに同じです。
自分らしさを大切にしながらも、他者を思いやり、共に生きることを学ぶ
それが、社会の中で自分の居場所を見つけていくための“生きる力”になると、私たちは信じています。